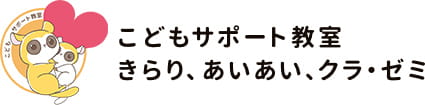小さい「や」「ゆ」「よ」は言うことはできても、読んだり書いたりすることが難しいんです。
日本語の「かな」はそれぞれ1つずつに異なる読み方があります。でも、小さい「や」「ゆ」「よ」自体はそれだけでは読めないですよね。
「や」は「ya」と読むように教えられ、せっかく読めるようになったのに、小さく表記されると別の読み方になるのです。母音をのばす「長音」も同じですし、つまる音の小さな「つ」も同じ。
このように、単独では読めなくて、何かとくっついて初めて発問できる文字(むしろ「記号」ととらえた方がよいのかも)を読んだり書いたりするのはとても難しい。さらにカタカナの「ロープ」はひらがなでは「ろおぷ」と表記するなど、カタカナとひらがなの違いもあり、文字を習得し始める頃のお子さんにとっては大混乱。
そこで、こんな支援ツールを作りました。
まずは「動物の鳴きマネ遊び」。「わんわん」から「わっわっ」のように「息をとめる音」(つまる音=促音)の感覚を知ってもらいます。
支援者が発音した言葉を文字チップでつくるクイズにチェレンジ。

次に、写真カードを見て、どこに小さい文字が入るのかを充てるクイズにチャレンジ。

正解したときは「やったあ」と大喜び。遊びながら、操作する過程を楽しみながら、言葉の理解を深めていきます。
(文章を入力しながら、改めて気づきました。拗音、促音のなんと多いことか。日本語は拗音、促音があふれている。)