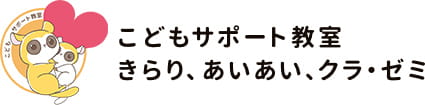(前回からの続き)
そしてもうひとつ大切なのは見通しがもてるかどうかです。
例えば、スケジュール管理のできないお子さんは大変です。学校のテストは1週間ぐらい前には発表されるはず。でもその事は忘れてしまって、数学のテストが迫っているのに社会のワークをやってみたり、逆に社会のワークの提出日が迫っているのに、数学のワークをやってみたり。
だからこそ、「計画をたてる」「予定をたてる」という先を見通す力を「家庭学習を通して」つけてあげたいもので
す。
「きらり」多治見校でも中学生ぐらいのお子さんには、「今日のきらりの予定」をたててから学習支援をすることがあります。これがまず第一段階です。第二段階では、支援の終わりに「次回のきらりの予定」をたてます。次は1か月の「きらりの予定」をたてます。少しずつですが、「そのつもりでいる」という状態を作るのです。
発達に凸凹のあるお子さんは、「予定」をたてて実行することが苦手です。まず、予定を把握していない。もしそこができなければ、学校の先生に合理的配慮の1つとして、「予定をタブレットで写すところまで見届けてほしい」とお願いしてはいかがでしょうか。最初は目や手をかけていただいて、少しずつ自分でできるように(=自立)手助けしていただくようにお願いしてみてはいかがでしょうか。
ご相談を受けた保護者の方には今まで述べたように、「家庭学習のポイント」「動機づけ」「予定・計画」の3点についてお話させていただきました。
家庭学習の終わったお子さんに絶対にかけてはいけない言葉があります。
「もっとていねいに書いたら」「この漢字のここはハネルのよ」「この計算ちがっているよ」
終わってほっとしているお子さんはどう思うでしょうか。
私はかつて息子に「おれのやることに いちゃもんばかりつけやがって」と言われたことがあります。子どもがそう言いたくなる気持ち、今なら痛いほどわかります。
じゃあどう考えたらいいの?
過去のコラムをぜひお読みください。
合理的配慮に関しては次のコラムもお読みください。